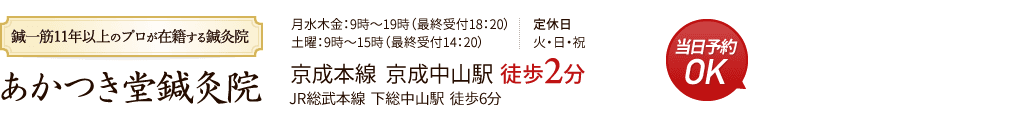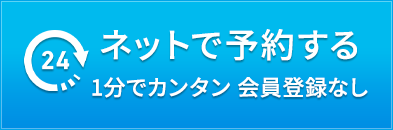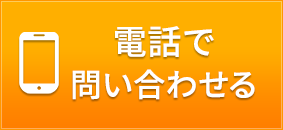500mほど歩くと腰が痛くなる、60代
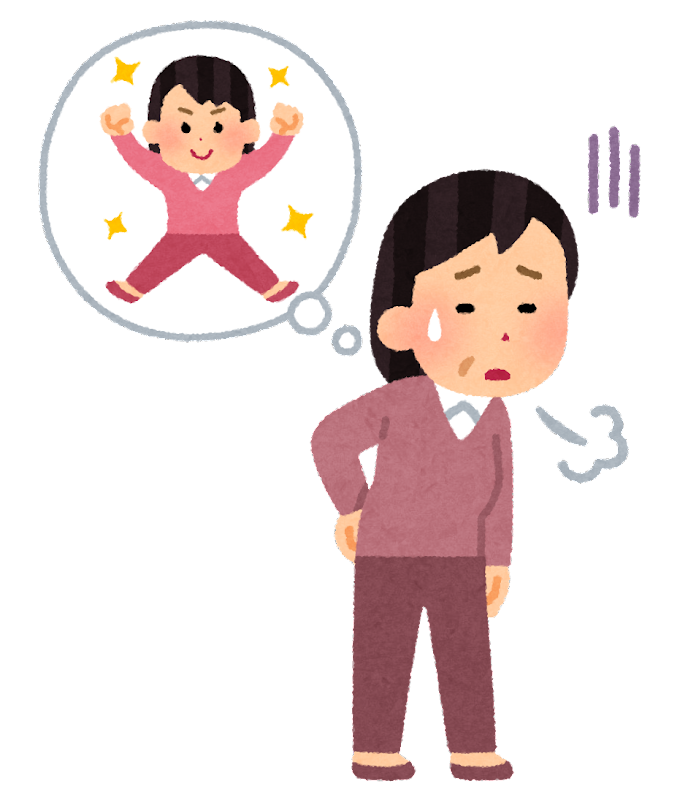
歩くと痛む腰──その正体のひとつは「皮膚」だったかもしれない
「500メートルほど歩くと、腰や股関節が痛くなる」
60代の男性が来院された。普段の生活では特に支障はないものの、500メートルほど歩くと、腰から股関節にかけて痛みが出るというお悩みであった。整形外科での検査は受けておらず、画像上の異常も確認されていない状態。
⸻
腰の痛み。でも、触れてみるとどうやら痛みの要因は腰そのものではなかった。
痛みの出る部位は腰や股関節まわり。
けれど触診を進めていくと、実際に強い反応があったのは、背中の上部から腰にかけての皮膚表面。
筋肉の緊張というよりも、皮膚自体が乾燥気味で硬く、柔らかさが失われている印象。
これは「皮膚が筋肉や関節の動きを間接的に制限している」という感覚に近いものだった。
鍼を“刺さない”──接触鍼という選択
この方には「接触鍼(せっしょくしん)」という、鍼を皮膚に軽く当てるだけの施術を行った。
筋肉や深部には触れず、皮膚という“もっと浅い層”に対して、ごく穏やかな刺激を与える方法である。
回を重ねるごとに、皮膚の硬さは徐々にやわらぎ、歩行時の痛みも軽減した。
4回目の施術を終える頃には、ご本人の動きにも明らかな違いが現れていた。
皮膚という「感覚器官」について
皮膚は単なる外側の膜ではなく、触覚・温度・痛覚など、あらゆる感覚を通して外界とつながっている。
発生学的に見ても、皮膚は外胚葉由来で、脳や神経系と同じ起源を持つ。
皮膚への刺激は通常、脊髄神経を経て脳の体性感覚野へと伝達され、感覚として認識される。
一部では「皮膚そのものが刺激情報を局所的に処理するのでは?」という仮説もあるが、現時点では明確な科学的根拠は確認されていない。
それでも臨床の現場では、皮膚の状態が動作や痛みと関係していると感じるケースは少なくない。
とはいえ、「皮膚が硬い」という感覚は、患者さんにとっては非常にわかりにくいものである。
比較する経験がない方にとって、自分の皮膚が「硬い」「動かない」と言われても、
なにが正常でなにが異常か、ピンとこないのが当然である。
それを言葉だけで説明しきれないことも、私自身、毎回感じている。
「ここ、硬いですよね」と言われても、
「そうですかね…?」という反応が返ってくることも多い。
だからこそ、結果として変化を感じてもらえたときは、どこかほっとしてしまう。
結果は大体予測通り。でも、、
この症例では、皮膚の状態と痛みの程度が一致しており、施術による変化も予測に近いものでした。
けれど同じような症状を訴える方でも、皮膚に硬さが見られない場合や、逆に皮膚が硬くても症状に影響していないように見えることもあります。
そうした「一致しない症例」をどう読み解くか。
それが今の自分にとっての大きな課題です。
「痛む場所」だけではなく「何が起きているか」をみる
痛みの正体がいつも明確に見えるわけではありません。
でも、体のどこに動きの引っかかりがあるのか、
そこにどうアプローチすれば変化が生まれるのか──
それを一緒に探る過程こそが、鍼灸という方法の核心かもしれません。
皮膚は、見落とされやすいけれど、とても大切な“感覚の窓口”です。
今回の症例は、そのことを改めて思い出させてくれました
もうひとつ、個人的に課題だと感じているのは、
この「皮膚の硬さ」という感覚を、どう伝えれば納得してもらえるのかという点です。
皮膚は、日常的にあまり意識される場所ではありません。
「痛み」や「張り」は感じられても、
「皮膚そのものが硬い」と言われても、それがどんな状態なのか想像がつかない。
まして、一般の方が他人の皮膚と比べる機会もほとんどありません。
今回のように、施術を重ねることで明らかな変化が出た場合は、
あとから「あ、そういえば…」と振り返ってもらえることがあります。
でも、そうならなかったときに、
言葉でどう説明し、納得感を得てもらうかは、私にとっての永遠のテーマなのかもしれません。