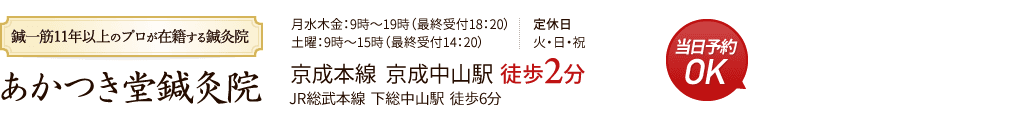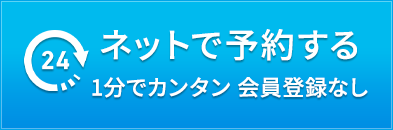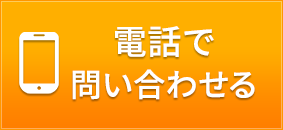英語·アート·鍼灸──「通じること」とは何か?

こんにちは。今日は「英語」と「アート」という、一見まったく異なるふたつの営みについて考えてみたいと思います。
そしてその先に、もうひとつの表現行為としての「鍼灸」についても視野を広げてみたいと思います。
近年、翻訳AIや画像生成AI、音楽生成AIの発達により、英語もアートも「できること」そのものの価値が相対的に下がってきました。
英語を話せることも、絵を描けることも、もはや“特技”とは言いにくい。
そうした変化の中で、多くの人が立ち止まり、問い直しています。
「私たちは、なぜ英語を学ぶのか? なぜアートを表現するのか?」
この問いへの糸口は、「通じることの本質」にあるのではないかと思います。
英語は、「意味を正確に伝えるための道具」です。
文法や語順といったルールが厳密に存在し、それに従ってこそ、他者との意味の共有が可能になる。
言い換えれば、通じなければ英語としては“失敗”なのです。
一方でアートはどうでしょうか。
アートは「意味を伝える」ことよりも、「感じさせる」こと、「問いかける」ことに重きを置きます。
つまり誰かに理解されることを目的としなくても、成立する。
むしろ、「なぜ自分はこれがわからないんだろう?」と観る人が思った瞬間、すでに対話が始まっている。
アートは、言葉にできない感覚、矛盾、曖昧さ、空白、そうした“説明不能なもの”にこそ向き合い、私たちの内面に波を起こします。この違いは、AIとの関係においても際立ちます。
英語は構造化されており、AIは非常に高精度に模倣できます。
翻訳や要約は、すでに人間以上のスピードと正確さを持っています。
一方アートは、表面的なスタイルを模倣することはできても、その内側にある「なぜこの形になったのか」という動機やゆらぎまでは再現しきれません。
言い換えるなら、英語は「世界を整理する言葉」、アートは「世界を問い直す行為」。
そして私はこの視点を踏まえたとき、「鍼灸」という営みもまた、そのあいだに立つものなのではないかと感じるのです。
鍼灸は、言語でもあり、アートでもある鍼灸という行為
これも、「通じるか/通じないか」のあわいに立つ表現です。
一見、鍼灸は技術であり医学です。
経穴、経絡、陰陽、五行など、体系化された理論が存在し、それに基づいて施術される。
この意味で、鍼灸は「言語」に似ています。
施術者は鍼という言葉を用いて、患者の身体に何かを語りかけている。
そして、それが身体に通じたとき、ある種の反応や変化が生まれる。
しかし、すべてが理論通りに伝わるわけではありません。
同じ理論に従っていても、患者によって反応は異なるし、同じ患者でも日によって身体の“返事”は変わります。
刺す角度、深さ、呼吸、場の空気、沈黙の気配――それらは数値化できない曖昧さをまとい、施術者は感覚的に「読む」「感じ取る」「委ねる」しかありません。
つまり、鍼灸は「通じること」を前提としながらも、
「通じなさ」を含み込んだ行為といえるのではないか。
それはまるで、英語のような構造性と言語性を持ちながら、同時にアートのような身体的·感性的·空間的表現としても機能している。
たとえば、あるツボに鍼をしたとき、身体がまるで「それ、今は違う」と言っているかのような反応を返すことがあります。
逆に、思いがけないところで「あ、それです」と言わんばかりに、ふっと気がゆるむような場面もある。
それは、施術者と患者の身体との“無言の対話”です。
言葉では説明できないけれど、確かにそこにある“やりとり”です。
このとき、鍼灸という行為は、まさに「表現そのもの」になる。
通じれば響き、通じなければ沈黙する。
そのあいだに立ち上がる反応こそが、鍼灸という営みの核心なのかもしれません。
- 英語は「整理された世界を共有するための道具」
- アートは「整理しきれない世界を問い続ける行為」。
そして鍼灸は、その両方を含みながら、人と人とのあいだに立ち、“見えないこと”を見ようとする実践です。
AIが“通じること”を容易に再現できる時代だからこそ、通じる/通じないのあいだで揺れ続ける行為、それ自体が、人間が人間として生きる意味になっていくのではないでしょうか。
英語では「通じなさ」は失敗であり、アートでは「通じなさ」すらも価値になります。
そして鍼灸は、その両方の間に揺れながら、私たちに問いかけてくるのです。
あなたの体に、この言葉(鍼)は、今、通じていますか?
と。
院長のひとりごと
さて実は今回のメイントピックはチャットGPT(生成AI)を駆使して制作しました。
この生成AIが台頭しつつある世界で、我が子が英語を学ぶことと美術(アート)を学ぶことの意味にどれだけの意味があるのかという疑問をチャットGPTに問いかけて対話しニュースレターにしてくれと依頼したのです。
ほぼ全文AIが作成しました。(修正したい箇所が30%ほどあるのですそれですと、今回の私の意図が伝わりにくいと思ったためあえてそのまま載せました。)
この院長のひとりごとコーナーはちゃんと私が書いています。
私がAIに相談することで、私が「今私が感じてはいるが言語化できないことはなにか?」について、その答えの輪郭が生成AIを利用するよって見えてくるのです。
今回のニュースレター制作にあたり、「英語(言語)にはルールがありそれを逸脱すると通じない。
でもアートはその通じないということからはじまる表現があるでは?」
とAIに言われたとき、「あ、そうかも!?」と膝を打ったのです。
考えの輪郭が浮かび上がる
自分の考えていることを整理させ、必要に応じて加筆修正してくれる。
「きっとあなたが考えていることってこういうことじゃない?」と。
こんなことができるようになったのです。
実に驚くべき世界が来たのだと思います。(とはいえこんなことはまだまだ序の口でしょうが。)
そう考えたときやはり、私や我が子がこれからなにを学び何をしていくかということを考えていかねばならないと思うのです。
英語やアートという表現方法の価値が下がる。
つまりこれらが一般化しつつあるこの世の中で、それでも学ぶことに価値はあるのか?
英語もアートも機械で代用できる、それでもじゃあなぜ学ぶのか?
その問い自体をAIに言語化されようとも、私自身から湧き起こってくるなにか「衝動」のようなものをこれからも大切にしていきたいものです。