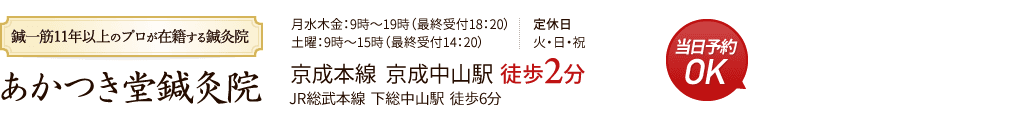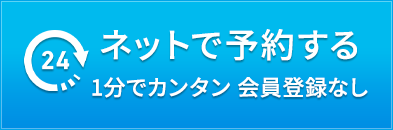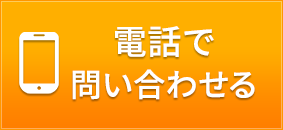鍼灸治療、キレイゴトのその先へー

「わからない」ということからしか生まれない信頼があると私は思っている。
たとえば私にとって「今の症状がどこから来ているのか、正確にはわからない。
でも、こういう可能性がある」と語るような会話はとても勇気のいることだ。
施術者としては、できるだけ的確に答えたいし効果を出したいという気持ちが当然ある。
けれど、その場で断言できないときに「わからない」と伝えるのは、自分の不完全さをさらす怖さすら伴う。
だからこそ「わからないけれど一緒に考えたい。
誠実さを伴う
この道筋かもしれない」と言えることには誠実さが宿るのだと思う。
誠実さがなければ「わからないから仕方ない」と放り出すこともできる。でも、それでは信頼にはつながらない。
ということは、ひょっとすると「誠実である」とは答えを持っていることではなく、「問いを手放さない」ことなのではないか。
そんなふうにも思う。
「まだわからない。でも、今できる最善を尽くしたい」
その姿勢を持ち続けることで、患者さんとのあいだに対話が生まれるのではないか。だとしたら、その問いを共有することこそが、関係の出発点になるはずだ。
たとえば足のしびれが取れないとき。
症状のある部位だけを追っても変化が見えないとき。
それでも、他の部位との関係を探ってみる。
過去の病歴や生活のパターンを丁寧に聞き直してみる。
場合によっては文献を調べ、別の視点から見直してみる。
そうやって「まだ見えていないもの」を探す過程には、治る・治らないという結果を超えた、人間同士のやりとりがあると思う。
もちろん、どうしても変化が出せないこともある。
無力さを痛感する場面もある。
けれどそのときに「無力である自分」としてそこに留まるのか「まだ可能性があるかもしれない施術者」として向き合い続けるのか。その態度の違いは、患者さんに必ず伝わる。
信頼というのは「全部うまくいく」ことではなく、「一緒に考え続けられるかどうか」で育つものだと思う。
結果が出ないときでも、「この人は、ちゃんと考えてくれている」「本当に向き合おうとしてくれている」と感じてもらえるかどうか。それこそが、鍼灸という曖昧なものの中で、いちばん確かな手応えなのかもしれない。
そしてその手応えは、いつか結果として現れることもあるし、結果にはならなくても「ここに来てよかった」と思ってもらえる何かを残すこともある。
私は、そんな治療のかたちを信じていたい。
キレイゴト
……そんなことを考えるけれど、所詮これは綺麗事でもある。
信頼だの誠実さだの、美しい言葉を並べることはできる。だが、実際には結果が出なければ、患者は離れていく。
そしてそれは、いつでも起こり得るし、実際に起こる。
そして何より、施術者の側にだって「飽き」は訪れる。
考えて、試して、また外れて、、を繰り返すなかで、ふと「もういいや」と手放したくなる瞬間がある。毎回すべての症例に、100%の集中力と関心を注げるわけではない。
自分のモチベーションや生活のコンディションだって、当然ながら日々揺れ動いている。
それでも、考え続けなければならないと思う。
飽きたときこそ、問い直さなければならない。
ある種の暴力
「自分はなぜこの仕事をしているのか」
「どこまでが惰性で、どこからが信念なのか」
鍼灸という行為は、そもそも「結果」と「過程」が曖昧に入り混じっている。
科学の世界で重んじられる「再現性」は、もちろん重要だ。しかし、ヒトの身体は自然の一部であり、一定に保たれるべき「実験条件」そのものが、そもそも存在しない。
同じように見える腰痛でも、ある人は仕事のストレスで悪化し、ある人は天候に反応し、ある人は既往歴が関係している。
表面的な症状が一致していても、背景も、身体の層も、まったく違う。
つまりその意味では「同じ症例」は存在しないと言っていい。
それならばそこに「再現性」を求めることは、ある種の暴力ではないのか。
自然を、ヒトをある型に押し込もうとすること。
たしかに、科学は「何がどれくらい効いたか」を測るために不可欠な道具だ。だがそれが「効くかどうか」という問いのすべてを規定してしまうとき、本当に見なければならないものが、こぼれ落ちていく。
これは、僕ら鍼灸師が日々、言語化せずとも感じていることのはずだ。
だから、鍼灸は科学的な指標だけでは測りきれない。変化の予兆や、患者の語る身体感覚、あるいは施術者自身の手の中に残る微細な感触、そうした曖昧な手がかりのなかから「いま何が起きているのか」を少しずつ読み取っていく作法なのだと思う。
もちろん、それは不安定で、曖昧で、時に当てにならない。けれど、その不安定さのなかにこそ、現実の身体のダイナミックさがある。
割り切れるのか
「効いた・効かなかった」だけで世界を割り切ることに、私は慎重でありたいと思う。
たとえば、それが今週は効かなかった。でも来週、効き始めるかもしれないようなものだとしたら?
私たちの仕事は、その見えにくい時間の流れにも、手をかけることではないかと思う。
科学と矛盾しないためではなく、科学からこぼれ落ちたものに触れるために、鍼灸があるのだとしたら。
飽きても、わからなくても、何も変わらなくても、それでも手を止めず、考え続けること。
その行動こそが、鍼灸治療の本質であり「臨床」なのかもしれない。